劇場・ホール・会館情報(冬)
冬の劇場・ホール・会館情報
冬には、全国各地の劇場やホールで音楽を始めとする様々なイベントが開催されます。外は寒い季節でも、劇場内でのイベントで心が温まる体験ができるのも冬の楽しみ方のひとつと言えるでしょう。
規模も種類も様々!クリスマスコンサート

12月になると街はクリスマスの雰囲気に包まれ、劇場やホール、会館も冬らしい催しものが行なわれています。クリスマス・イヴの前あたりから、クリスマスソングや賛美歌、ゴスペルなどがコンサートホールで行なわれ「クリスマスの雰囲気を味わいたい」と多くの人が訪れます。コンサートの規模や種類もバラエティに富んでいるため、自分に合ったクリスマスムードの会場を探すことも可能です。
劇場ではクリスマスムードがたっぷりと詰まった劇が鑑賞できるところもあります。客席が2,000席を超えるクラスの大きなホールでは、フルオーケストラによるクリスマスコンサートも行なわれると言います。有名な指揮者や歌手が出席するイベントのチケットはこの時期、数ヵ月前に予約しておかないと入手が困難です。クリスマスやお正月などは、会館にて子ども向けのイベントや寄席が行なわれている場合もあります。
紅白歌合戦のメイン会場・NHKホール
大晦日の夜にはNHKの「紅白歌合戦」を見ないと年が越せない、という気分の人も多いでしょう。1951年(昭和26年)から続く紅白歌合戦は、番組のスタート当初は正月番組でしたが、第4回の1953年(昭和28年)以降は大晦日の夜に生放送で中継される、言わば大型ライブ番組です。
紅白歌合戦のメイン会場として1973年(昭和48年)から使用されているのが、「NHKホール」です。東京都渋谷区のNHK放送センターに隣接するホールで、1972年(昭和47年)に完成して以来、紅白歌合戦を始め多くの番組収録や生放送の現場として利用されています。その座席数は1階に1,091席、2階に1,335席、3階に1,175席の合計3,610席で、この規模はアメリカ・ニューヨークの「メトロポリタンオペラハウス」の3,800席やイギリス・エディンバラの「エディンバラプレイハウス」の3,060席に匹敵する大きな規模のホールであり、ニューヨークの「カーネギーホール」(2,800席)やオーストラリア・シドニーの「オペラハウス」(2,680席)、そしてニューヨークのブロードウェイで最大と言われる「ガーシュウィン座」(1,930席)を凌ぐ規模となっています。
これだけの収容人数を誇る大きなホールでありながら、NHKホールは客席から見たステージとの距離感が近く、臨場感たっぷりに観賞を楽しむことができるのも特徴のひとつです。そのことも、大晦日の紅白歌合戦が長い間、高い人気を保っている理由のひとつなのかもしれません。
市民会館は大きな同窓会会場?
1月の第2月曜日は「成人の日」と定められ、全国各地で成人式が執り行なわれます。山村などの人口減少地域では、その地域の小学校で成人式が開かれるケースもありますが、多くの場合、市区町村の地域会館や市民会館で行なわれることが一般的です。成人式が今日のような開かれ方となったのは、1946年(昭和21年)の埼玉県蕨町(現在の蕨市)で開催された「青年祭」であるとされています。太平洋戦争が終わって数ヵ月の暗い時勢に、これから始まる明るい未来への希望を若い人たちに持ってもらうために企画されたイベントで、この年に20歳を迎える若者たちを祝した「成年式」もここで開催されました。この成年式がその後全国へと広まっていき、現在の成人式へと発展していったのです。
成人式ではその地域の会館にスーツや晴れ着で着飾った新成人が集まり、壇上ではその自治体の首長や教育委員会長などがお祝いや励ましのスピーチをします。しかし、進学や就職で離れていた旧友との再会が多い成人式の会場では、壇上に立つ大人のスピーチを聞くよりも久しぶりに会う友人と近況報告をし合うことの方が楽しいため、会館は言わば大きな同窓会の会場のような雰囲気となるのが一般的です。



年末年始の時期、劇場・ホールではいろいろなイベントが開かれ、多くの人が足を運びます。特に正月は華やかなイベントが多く、一年でホールが最も盛り上がる時期だと言えるでしょう。
カウントダウンライブ

毎年大晦日から元旦にかけて、各地のホールやアリーナではカウントダウンライブが開催されます。カウントダウンライブの開催が増えるにつれて、劇場やホールで新年を迎える人も増えてきました。年越しと言うと、昭和の時代なら家で紅白歌合戦を見て、初詣に行くのがひとつのパターンになっていましたが、みんなで年が明けたことを祝うイベントが増えてきたこともあり、年越しのスタイルも変化しつつあります。
カウントダウンライブは、通常のライブやコンサート以上にアーティストのテンションが高く、通常とは違った特別なパフォーマンスが披露される場合も多くあることから会場も大いに盛り上がり、熱気が渦巻きます。年が変わる時刻が近づくと、アーティストがステージからカウントダウンを呼びかけ、『ゼロ』、の瞬間にはステージも客席も一体となって新しい年を祝います。カウントダウン後には、そのアーティストの十八番(おはこ)やヒット曲を中心としたプログラム構成が定番となっており、終演までクライマックス並みの興奮が続きます。
好きなアーティストと新年を迎える喜びを共有できるのは、カウントダウンライブならではの楽しみです。1年の締めくくりと始まりの瞬間を、感動と興奮に包まれながら過ごしてみてはいかがでしょうか。
歌舞伎の日(2月20日)
歌舞伎は日本の伝統芸能のひとつですが、国際的にも評価が高く、2009年(平成21年)にはユネスコの「無形文化遺産」に登録されました。その歌舞伎に関連した最も古い記録は、江戸時代初期の1603年、出雲阿国が「かぶき踊り」を踊っていた、という物です。1607年2月20日には、江戸城で徳川家康をはじめ諸国の大名の前で出雲阿国による「かぶき踊り」が初めて披露され、現在ではこの日を記念して「歌舞伎の日」に制定しています。
歌舞伎の草創期は、女性が踊る「遊女歌舞伎」が人気でしたが、トラブルが多く、「風紀を乱す」という理由で幕府によって禁止されました。そのため、歌舞伎は男性によって演じられるようになり、現在のスタイルが確立。江戸文化が花開く元禄時代になると、歌舞伎役者は大衆の人気を集め、東洲斎写楽や喜多川歌麿などの絵師によって歌舞伎が描かれるようになり、浮世絵には「役者絵」という一大ジャンルが生まれました。享保時代になると、歌舞伎の舞台そのものも発展し、それまでオープンだった舞台には屋根が付けられた他、せりや花道も設置されたことで、演出の幅も広がり、演劇としても大きく進化しました。明治から昭和の時代には、演目は古典だけでなく当時の世相を反映した物に広がり、大衆娯楽としての地位を確立。
現在の歌舞伎もまた、伝統を継承しつつも新しい要素を採り入れ、大勢の人を楽しませています。また、海外公演や映像などを通じて世界的なファンも獲得し、日本の文化的象徴のひとつにもなっています。
劇団公演
お正月のテレビドラマでは、特別編や新年スペシャルが放送され、普段よりも豪華な顔ぶれを目にします。これらの番組に出演する俳優には、劇団出身者が意外な程多く、劇団で芝居の腕を磨き、その表現力や演技力を買われて出演した俳優も珍しくありません。
日本では、専属の劇場や芝居小屋を拠点としつつ全国で公演を行なう大規模な劇団から、地方都市などでサークル的に活動している小規模な劇団まで、無数の劇団が活動しています。また、俳優志望者が集まる劇団や、宝塚歌劇団のように女性だけのミュージカルに特化した劇団など、その方向性も様々です。
大規模な劇団では、舞台で芝居をする役者以外にも、脚本や演出、舞台装置などの役割が分業化され、組織化された運営を行なう一方で、小規模の劇団は運営から演出、脚本執筆まで出演者がかねることも多く、手作り感あふれるお芝居が展開されます。また、規模としては小さくても、ある程度名前が知られていると、全国の劇場やホールなどを巡演することもあります。劇団公演は、テレビで見る俳優たちの演技に触れる絶好の機会でもあります。正月公演などで劇団の芝居を見る機会があれば、ぜひ足を運んでみましょう。
冬の劇場・ホールは、定番のコンサートや芝居が開かれます。ベートーヴェンが作曲した「交響曲第9番」と「忠臣蔵」は、いずれも日本でお馴染みの作品として親しまれています。忙しい最中ではありますが、1年の締めくくりとして、コンサートや芝居を鑑賞してみてはいかがでしょう。
第九を聴こう

年末になると全国でベートーヴェンの第九のコンサートが開かれます。第九とは、ベートーヴェンの交響曲第9番ニ短調作品12で、ベートーヴェンの最後の交響曲となっています。この交響曲の特徴は、第4楽章が独唱及び合唱を伴って演奏され、そのタイトルは「歓喜の歌」と名付けられています。そのため、コンサートではオーケストラの演奏を聴くだけでなく、一般の人が合唱に参加できる形式のコンサートもあります。
この交響曲は、それ以前の交響曲の常識を打ち破った斬新なもので、シューベルトやブラームス、ブルックナー、マーラーなどにも影響を与え、ベートーヴェンの傑作のひとつとされています。第4楽章の「歓喜の歌」は、日本だけでなくヨーロッパでも人気が高く、ヨーロッパ全体を称える歌としても知られ、欧州連合でも統一性を象徴する曲として採択されています。交響曲に声楽を使用するのは、あまり多くありませんが、交響曲全体に効果的に使われたのがベートーヴェンの第九が初めてで、それ以降もメンデルスゾーン、リストなどが声楽入りの交響曲を発表していますが、第九程大きな評価は得られていないようです。「歓喜の歌」は、フリードリヒ・フォン・シラーの詩「歓喜に寄す」から抜粋し、ベートーヴェン自身が編集して曲をつけたとされています。
交響曲第9番が初めて演奏されたのは1824年のウィーンで、演奏後は聴衆の大喝采に包まれました。日本では、1940年の大晦日に、紀元二千六百年記念行事の一環として演奏され、ラジオの生放送で紹介されことから、年末に「第九」が数多く演奏されるようになりました。また、戦後まもない時代でオーケストラの収入が少なく、年末年始の生活だけでも改善することと、合唱団が加わって演奏に参加するメンバーが多く、客の入りが良かったことも年末の演奏に繋がったようです。それが毎年恒例となり、各地で演奏会が開かれるようになりました。
今年の年末も「第九」を聴いて、1年の締めくくりにしましょう。
忠臣蔵
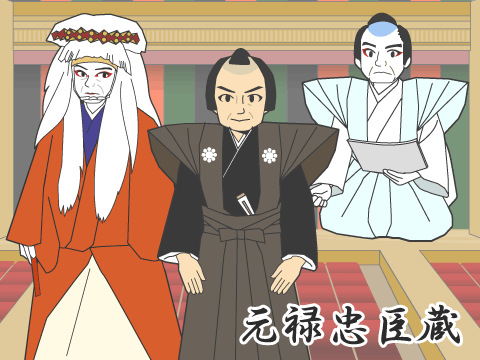
歌舞伎の演目のひとつに「仮名手本忠臣蔵」があります。赤穂浪士の討ち入り事件を題材にしたもので、主に「忠臣蔵」と呼ばれています。歌舞伎以外にも人形浄瑠璃の演目のひとつでもあり、他にも映画、テレビドラマなどで幅広く取り上げられており、日本で人気の高い芝居作品のひとつです。この討ち入りの日が12月14日であったことから、年末によく上演されたり放送されたりします。
1748年に初演されたこの作品は、二代目竹田出雲・三好松洛・並木千柳による合作で、当初は人形浄瑠璃のために書かれましたが、同年には歌舞伎の演目としても取り入れられました。そのストーリーは、江戸城松の廊下で、吉良上野介が浅野内匠頭に切りつけられ、浅野内匠頭はこれにより切腹し、浅野家も取り潰しとなりましたが、浅野の家臣である大石内蔵助らは吉良を主君の敵として、47人の士たちで吉良上野介邸に討ち入りし、主君の仇を討つ内容となっています。江戸中期の元禄期に起こった「元禄赤穂事件」を題材にしていますが、芝居としては多少脚色がしてあります。
仮名手本忠臣蔵は、全十一段から構成された大作で、歌舞伎では上演時間の関係から、内容を省略して上演し、すべてを上演することはありません。また、仮名手本忠臣蔵から派生した作品も数多くあり、中でも怪談と組み合わせた鶴屋南北の「東海道四谷怪談」は有名です。








